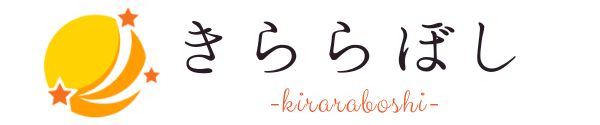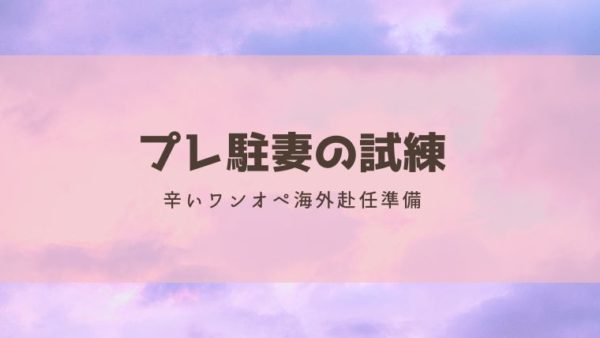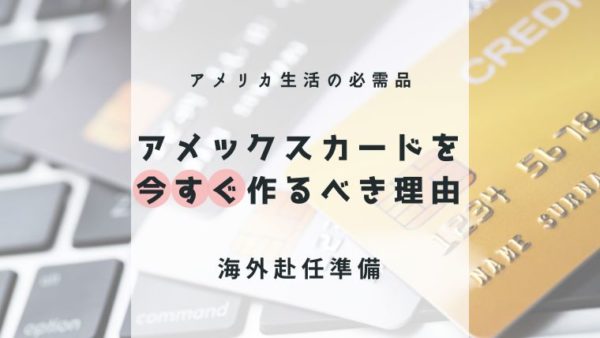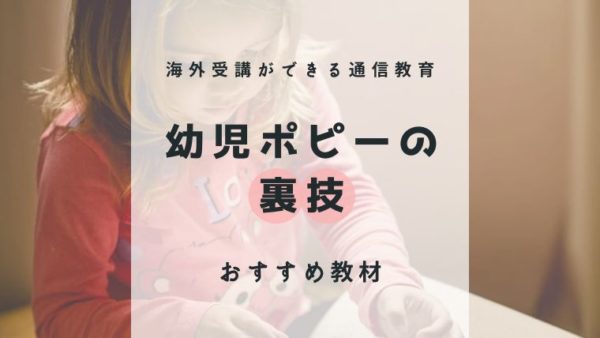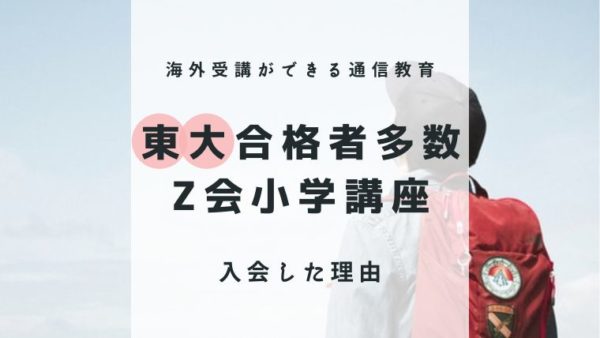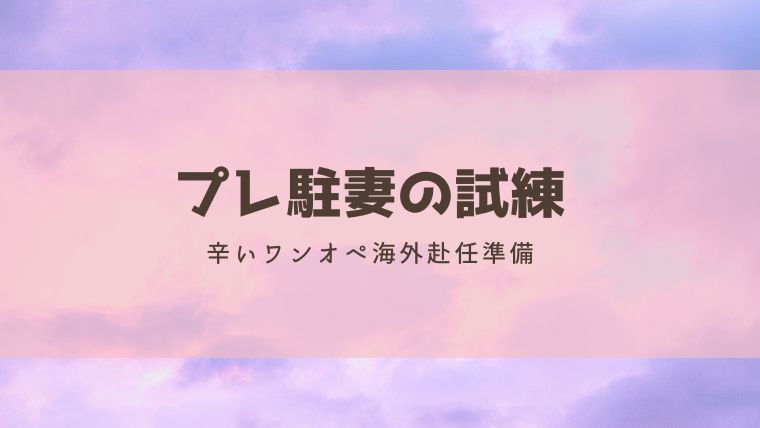
「海外赴任準備が辛い!」
「渡航前から鬱になりそう!!」
子連れでの海外への引っ越しは思った以上に大変です。
夫が既に渡航している場合は、実質ワンオペ育児をしながら、駐在準備をするハードワーク。
実際、海外赴任準備期間に体調を崩してしまったり、鬱になってしまったりする方はとても多いです。
私の知人は、出産後に赤ちゃんを連れて渡航する予定でしたが、精神状態が不安定になってしまい、最終的に夫は単身赴任になってしまいました。
私も、夫が渡米してから、精神的にも体力的にもキツイ日々を過ごしていました。しかも、普通では考えられない不測の事態が続出したのです。
家族帯同タイミングは?わが家の渡航スケジュール

会社によってスケジュールは異なりますが、ある程度暮らしの基盤を整えてから、家族を呼び寄せるタイミングが多いです。
夫の会社の場合、家族帯同の時期は、本人が渡航して6か月後でした。
実際に、渡航タイミングを決める際、考えなくてはいけないのは、この3つ。
- 夫の会社の規定
- 子供の幼稚園や学校への編入学のタイミング
- 妻の仕事の区切り(退職や休業など)
海外に慣れている方であれば、上司の承認を得て、6か月よりも前の時期でも可能だそうです。
と言うことで、まずは夫が8月に渡航。家族帯同の時期は、以下の理由から次の3月末にしました。
- 会社の規定で、家族帯同の時期が6か月後
- 子供(当時小学3年生&年中)の学年を終えてから渡航したい
- 確定申告をスッキリ終わらせてから渡航したい
私は、フリーランスで働いていたので、12月に廃業届を出し、2月に確定申告をするという流れが事務処理上、一番スッキリしていました。
ただ、世界を揺るがす新型コロナウイルスの影響により渡航を延期することになってしまい、完全に計画が狂いました。
家族帯同の渡航タイミングをまとめるとこんな感じです。
夫が単身で渡米しました。
夫が一時帰国し、子供二人と私が渡米予定でしたが、コロナで延期。
夫は一時帰国せず、子供二人と私が渡米。
結果的に、夫は約1年間単身赴任生活をすることになってしまいました。
子連れ海外赴任準備が大変な理由

もともと、不在がちの夫。中国に単身赴任をした時期もあり、一人でも大丈夫だと思っていました。
冷静に考えれば分かりますが、完全ワンオペ育児に加え、慣れない海外赴任準備もしなくてはいけないため、大変でないはずはありません。
① ワンオペ育児が限界
渡米予定日の直前は、イライラと疲れがたまって、暗黒の子育て時期でした。
毎日、鬼の形相で、子どもにとっては良い環境ではなかったですね…。(かなり反省しています。)
わが家は、両方の実家が遠方にあります。
5年前に、転勤で神奈川に引っ越してきて、仲の良いママ友はできましたが、地元でもありません。
夫は、長期出張や単身赴任も経験しているので、ワンオペ育児は慣れたもんでしたが、7か月間、全く会えないのは初めて。
子どもたちの運動会も、お遊戯会も、何もかも一人でした。
長男くんは、小学校のサッカーチームに入っており、土日がほぼ試合。
リアルクレヨンしんちゃん状態の次男くん(当時4歳)を連れて引率をするのは、並大抵のことではない。
三人揃ってで高熱が出たときは、カオス。
とりあえず、ネットスーパーがあったからよかったけど、どうやって生き延びたかよく分かりません…。
② とにかくやることが多い
自分も帰国子女なので海外に住んだ経験はありますが、夫の海外赴任に帯同するのは初めて。
手続き関係なんてチンプンカンプン。
夫の会社では「配偶者向けの海外渡航マニュアル」は、用意されておらず、全てイチから自分で調べなくて、こなしていかなくてはいけませんでした。
特に大変だったのが「予防接種」です。
アメリカは州によって、必要な予防接種が異なるので、ややこしい。
夫に現地校に行ってもらい確認すると、いくつか追加しなくてはいけないものもありました。
B型肝炎は、渡航前に3回打つ必要あったり、おたふく風邪になったのに抗体検査させられたり、生ワクチンのポリオだったせいで追加しなくちゃいけなかったり…。
長男くんが、まだ赤ちゃんのとき、同時接種が怖くて、1本ずつずらして打っていましたが、もう「打てるだけ打ってください!」と、強行突破。
渡米予定日の1週間前に、学校編入に必要な予防接種を全て打ち終えることができました。
③ 引越し準備を一人でやらないといけない
家族4人分の引越し準備、女性一人でやる量じゃない!
ガッツリ家族世帯用の家具家電が揃えられた家を片付けるのは本当に大変です。
近年はゴミの分別が厳しくて、引越し業者もノータッチ。
引っ越し日までに、冷蔵庫や洗濯機といった大型家電も、自分で処分しておかないといけません。
売れそうなものはメルカリで出品。送料がかかったり、状態があまりよくなかったりするものは、近くのリサイクルショップに持っていきました。
大型家具や家電は、自宅まで引き取りに来てくれる業者を探しました。
予測不能なハプニング続出

人生何が起きるか分からない。
海外赴任準は、ただでさえストレスがかかるのに、わが家の場合は、普通では考えられないほどの非常事態が起きました。
新型コロナ感染拡大でパニック
新型コロナの感染拡大で、世界各国大パニック。
日本では、学校が休校になり、子どもたちも家にいるようになりました。
引っ越し準備も、子どもたちが家にいることで、思うように進まないことも多かったです。
日本の感染が広がり、渡米が怪しいと思っていたら、今度はカリフォルニア州でも緊急事態宣言。
アメリカへの不要不急の渡航も自粛になりました。
実は、カリフォルニア州全体がロックダウンを決めた当日、夫は家族を迎えに来るために、一時帰国してきました。
ですが、あれよあれよと、アメリカへの渡航レベルが上がり、私たち家族は渡航延期に。
延期が決定したのは、引越し日のわずか3日前と本当にギリギリでした。
結局、夫だけ再度アメリカに戻り、また母子家庭生活に逆戻り。

マイホームの売却
コロナパニックに比べたら、小さく感じますが、このバタバタの時期に、地方に残していたマイホームを売却しました。
突然、現在の借主さんから、買いたいという申し出があったんです。
名義人の夫は既にアメリカに引っ越しており、住民票も印鑑証明もない。
登記も貸金庫に入れており、色々と面倒くさかったので、夫が一時帰国時したときに手続きしました。
不動産業者や銀行との連絡、セッティングまでは、全て私が行なったので、かなり疲れました。

子連れ海外赴任準備のポイント
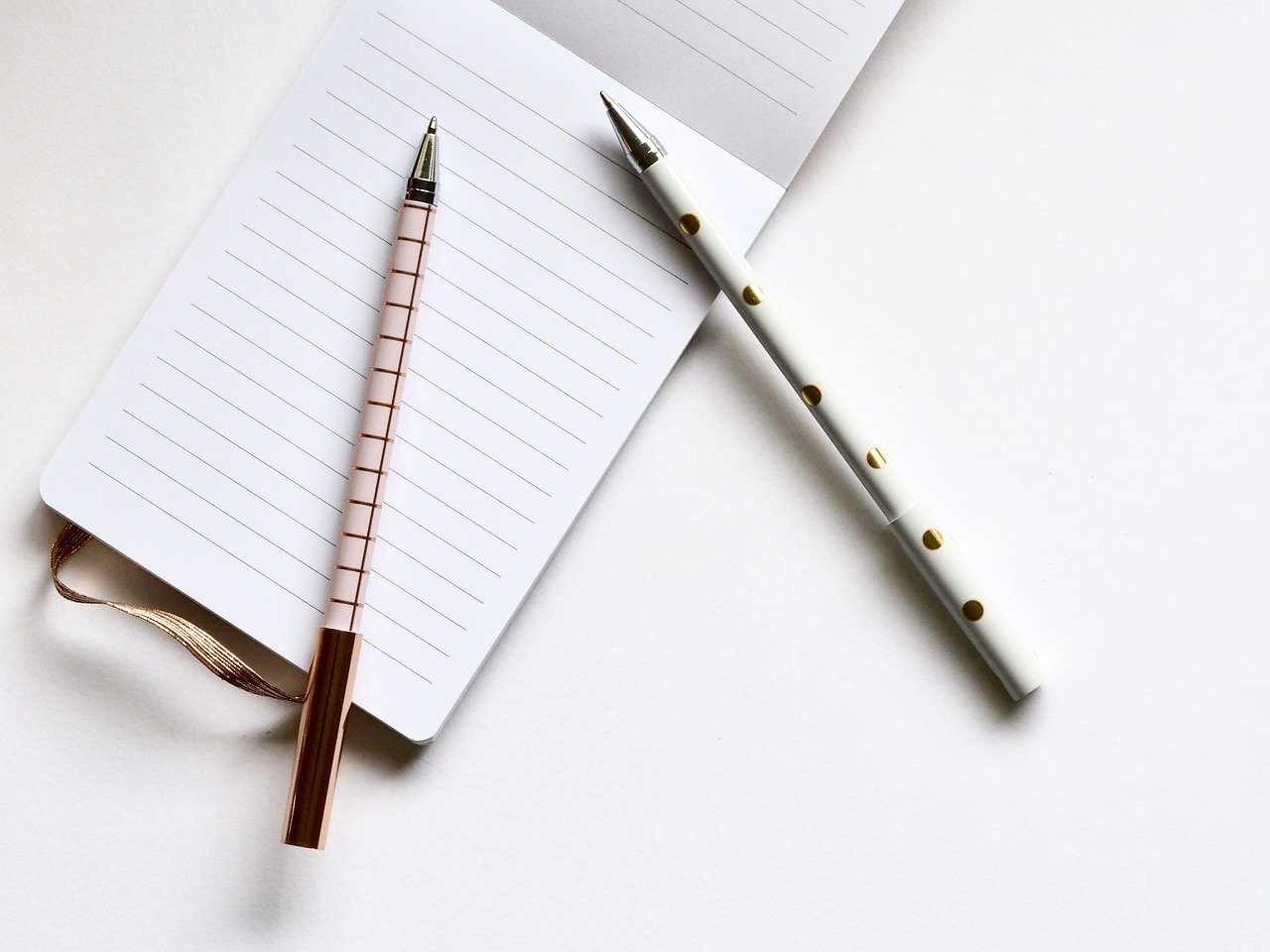
わが家のように、コロナウイルスのような非常事態が起きることは、本当に稀です。
何十年に一度という当たり年でした。(←どうせ当たるんだったら、宝くじとかがいい。)
ですが、新たな生活を踏み出すには、多かれ少なかれハプニングは付き物です。
実際に、ハプニングが起きたときに、落ち着いて対処するにはどうしたら良いのでしょうか。
① やることリストを作成する
海外赴任準備は、本当にやることが多いです。ハプニングが発生すると、どうしても思考能力が低下し、ミスが多くなってしまいます。
嘘みたいな話ですが、私の知人はパスポートを船便に入れてしまってあわや大惨事になるところでした。
海外赴任準備疲れで、普段では考えられない失敗をしてしまうこともあります。
チェックリストを作り、やることを見える化しておくことで、ある程度の予防ができます。
私も、やることリストを冷蔵庫に貼っておき、小まめに確認することで、大きなミスは減らせているようにに思えます。ただ、小さなミスはどうしてもありますよ。
私が作ったチェックリストで良ければ、使ってください 😉
② できることから早めに始める
計画通りに進むことがベストですが、思わぬハプニングが起きたときのため、できることから早めに始めることをオススメします。
例えば、大型家具の断捨離は、夫が渡航する前に済ませておくと楽です。
私自身、ミニマリストに憧れて、渡航が決まる前からソファや本棚など大型家具を処分していたので、かなり助かりました。
買い出しは、少しずつ揃えていくと負担が少ないです。
急に在庫がなくなり、欲しいものが買えないという事態もあります。
健康診断や人間ドックは、予約が取りにくいです。ギリギリだと受診できないこともあります。
また、再検査になったりしたときのことも考えておきましょう。
③ リアルタイムで情報収集を行なう
現地情報は、リアルタイムで確認できるツイッターが便利です。
テレビのニュースで流されるまでのタイムラグがあるので、最新情報は常にツイッターで見ていました。
現地にお住まいの方、同じように海外赴任準備を進めている方など、フォローしておくことで、いち早く有益な情報を知ることができました。
また、渡航予定の地域に住んでいる方のブログもよく見ていました。
他にも、海外渡航セミナーで知り合った人たちで、ライングループを作成し、情報交換をしていました。
先に、渡米した方からも現地情報が聞けるので、準備に役立てることができました。
結果、現地に住んでいる夫よりも精通している状態になっていました(笑)
私も、アメブロやツイッターをやっているので、何か質問などあれば遠慮なくご連絡ください。
無理せず海外赴任準備を進めよう

海外赴任準備は、本当に本当に大変な仕事です。
夫が先に渡航してしまうと、子供の世話をしながら、全て一人でやらなくてはいけません。
辛すぎて、リアルに泣きながらパッキングしていました。しかも、延期によってパッキングしたものを荷解きするというあり得ない事態に 😥
結婚はスタートとよく言いますが、海外赴任準備や引っ越しもスタートです。
現地に行ってからの生活を考え、周囲を目一杯頼りつつ、無理をしないで乗り切ってくださいね!